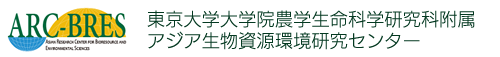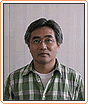
1957年松本市生まれ。東京大学農学部農業生物学科4年時より育種学研究室に所属し、1986年大学院農学系研究科博士課程修了、「オオムギα-アミラーゼの遺伝変異に関する研究」で農学博士の学位を得た。その後アメリカ国立環境衛生科学研究所(NIEHS/NIH)で2年間ポスドクをした後、1989年から農学部附属農場助手、1995年アジア生物資源環境研究センター助教授。
センターでは、植物の不良環境(ストレス)耐性機構の解明と耐性植物の開発に関する研究を行っている。これまで耐塩性、耐湿性、遮光(弱光)耐性などに着目し、耐性に関わる遺伝子の探索と機能解析を主として行ってきた。特にアジアで実際に問題とされている不良環境に対する耐性について研究を行い、フィールドで役に立つ研究成果をあげるようにしていきたいと考えている。実際、耐塩性に関する研究では、中国東北部で問題となっているアルカリ性塩類集積土壌に対する耐性機構について検討した。また遮光耐性は、混作が多く用いられ、樹間の耕地利用が求められているインドネシアで重要視されている形質である。
昨年から卒業生の柳蔘奎教授が所属する東北林業大学との共同研究として、黒竜江省ハルビン郊外の安達市のアルカリ性塩類集積土壌の植生回復と、耐性野生植物の耐性機構の解明、耐性遺伝子を用いた耐性植物の開発に関する研究を開始した。このフィールドを用いて、これからはより広範囲の専門分野の研究者との連携により、効率の良い植生回復手法を確立していきたい。柳蔘奎教授が安達市から貸与された200haの不毛な塩類集積地を、緑の草原・森林・耕地に変えるのが私たちの夢である。
研究室ホームページ
http://stress.anesc.u-tokyo.ac.jp/