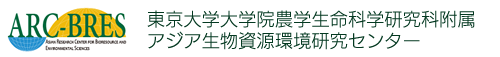1963е№ҙгҖҒеҘҲиүҜеёӮгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮ1997е№ҙгҒ«гҖҒдә¬йғҪеӨ§еӯҰиҫІеӯҰз ”з©¶з§‘еҚҡеЈ«иӘІзЁӢжһ—з”Је·ҘеӯҰе°Ӯж”»гӮ’дҝ®дәҶгҒ—гҖҒеҗҢе№ҙгҖҒгҖҢжңЁжқҗгҒ®жЁӘең§зё®еӨ§еӨүеҪўгҒ®ж°ёд№…еӣәе®ҡгҖҚгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҚҡеЈ«еӯҰдҪҚгӮ’жҺҲдёҺгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲдјҡзү№еҲҘз ”з©¶е“ЎгӮ’зөҢгҒҰгҖҒ1998е№ҙгҒ«гҖҒдә¬йғҪеӨ§еӯҰжңЁиіӘ科еӯҰз ”з©¶жүҖеҠ©жүӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ2004е№ҙгҖҒж”№зө„гҒ®гҒҹгӮҒз”ҹеӯҳеңҸз ”з©¶жүҖгҒ«й…ҚзҪ®жҸӣгҒҲгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ2005е№ҙ2жңҲгҖҒгӮўгӮёгӮўз”ҹзү©иіҮжәҗз’°еўғз ”з©¶гӮ»гғігӮҝгғјеҠ©ж•ҷжҺҲгҒ«жҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖе°Ӯй–ҖгҒҜжңЁжқҗеҠ е·ҘеӯҰгҖӮзү№гҒ«гҖҒгҖҺең§зё®жңЁжқҗгҖҸгҒ®иЈҪйҖ еҺҹзҗҶгҖҒз”ҹз”ЈгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҒи©•дҫЎгҖҒеҲ©з”ЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәзӨҺгҒҠгӮҲгҒіеҝңз”Ёз ”з©¶гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжңЁжқҗгҒҜдёӯз©әгӮ»гғ«ж§ӢйҖ дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз№Ҡз¶ӯгҒЁзӣҙи§’ж–№еҗ‘гҒ«жЁӘең§зё®еӨ§еӨүеҪўгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒең§еҜҶеҢ–гҒ•гӮҢгҖҒеј·еәҰзү©жҖ§гҖҒж„ҸеҢ жҖ§гҖҒеҠ е·ҘжҖ§иғҪгҒӘгҒ©гҒҢеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдҪҺиіӘж—©з”ҹжЁ№жқҗгҒ®жқҗиіӘж”№иүҜгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮ№гӮ®гҖҒгғ•гӮЎгғ«гӮ«гғјгӮҝгҖҒгӮӘгӮӨгғ«гғ‘гғјгғ гҖҒгӮҝгӮұжқҗгҒӘгҒ©гҖҒгӮўгӮёгӮўең°еҹҹгҒ®жңӘеҲ©з”ЁжқҗгҒ®з”ЁйҖ”жӢЎеӨ§гӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжЁӘең§зё®еӨ§еӨүеҪўжҠҖиЎ“гӮ’еҝңз”ЁгҒ—гҒҹжңЁжқҗд№ҫзҮҘгҖҒи–¬ж¶ІжіЁе…ҘжҠҖиЎ“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢз ”з©¶гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒжңЁиіӘгҒҢеј·йқұгҒӢгҒӨи»ҪйҮҸгҒ§гҒӮгӮӢзү№еҫҙгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҹең§еҜҶжңЁиіӘйҮҳгҖҒгғҖгғңгҖҒгӮ·гӮўгғјгғ—гғ¬гғјгғҲгҒӘгҒ©гҒ®жңЁиіӘжҺҘеҗҲе…·гҒ®й–ӢзҷәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢз ”з©¶гҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜвҖңз’°еўғдҪҺиІ иҚ·еһӢжңЁжқҗеҲ©з”ЁгҒ®жҸҗжЎҲвҖқгӮ„вҖңй«ҳеұӨжңЁйҖ е»әзҜүгҒ®ж§ӢжғівҖқгҒӘгҒ©гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®жңЁжқҗеҲ©з”ЁгӮ’гғ–гғ¬гғјгӮҜгӮ№гғ«гғјгҒҷгӮӢж–°жҠҖиЎ“гҒ®еүөжҲҗгӮ’зӣ®и«–гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еӨ–гҖҒгӮҝгӮұгҖҒгӮұгғҠгғ•гҖҒгӮөгӮӨгӮ¶гғ«гҖҒгғһгғӢгғ©йә»гҒӘгҒ©гҒ®жӨҚзү©з№Ҡз¶ӯгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹй«ҳеј·еәҰз№Ҡз¶ӯй…Қеҗ‘жқҗж–ҷгҖҒжңЁжқҗгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜиӨҮеҗҲдҪ“гҒӘгҒ©гҒ®й–ӢзҷәгҖҒеҢ–еӯҰеҮҰзҗҶгӮ„й«ҳжё©й«ҳең§еҠ зҶұеҮҰзҗҶгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮӢжңЁиіӘзҙ жқҗгҒҠгӮҲгҒіиӨҮеҗҲжқҗж–ҷгҒ®й«ҳеј·еәҰеҢ–гҖҒеҜёжі•е®үе®ҡеҢ–гҒ«й–ўгҒҷгӮӢз ”з©¶гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖд»ҘдёҠгҖҒж–°гҒ—гҒ„жңЁиіӘжқҗж–ҷгҒЁгҒқгҒ®еҠ е·Ҙжі•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҒзҙ жҠҖиЎ“гҒ®еүөжҲҗгҖҒй–ӢзҷәгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒжңЁиіӘгғҗгӮӨгӮӘгғһгӮ№иіҮжәҗгҒ®зҗҶжғізҡ„гҒӘеҫӘз’°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®ж§ӢзҜүгҒ«еҜ„дёҺгҒ—гҖҒгӮўгӮёгӮўең°еҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢз’°еўғе…ұз”ҹгғ»иіҮжәҗеҫӘз’°еһӢзӨҫдјҡгҒ®е®ҹзҸҫгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ
з ”з©¶е®Өгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮё
http://smd.anesc.u-tokyo.ac.jp/