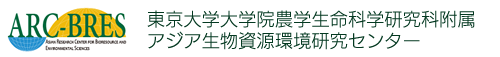問題土壌の環境修復と持続的利用
Environmental restoration and sustainable use of problem soils
ANESCでは平成20年度から22年度まで、日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業の日本側拠点機関として、アジア各国の研究機関と「問題土壌の環境修復と持続的利用」に関する研究交流を行いました。
(日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業についてはこちら )

研究交流目標
塩類集積土壌、アルカリ土壌、泥炭土壌、酸性硫酸塩土壌など、アジアで特に荒廃地化が進んでいる問題土壌をターゲットとし、それぞれの場所で交流相手国研究機関の研究者と共同してフィールド調査を行い、荒廃地に耐性のある野生植物や作物品種を探索し、環境ストレス耐性の生理機構の解析、遺伝解析、適合品種の育種、共生機能の解明を進める。これらの耐性植物や作物品種、共生系を用い、荒廃した環境を修復し、地域の社会経済条件に適合した広域の土地利用計画を策定し、生物資源の循環利用・生産システムを構築するための国際共同研究を行う。得られた成果を、各々の問題土壌地域個別的なものと、アジアの問題土壌地域の環境修復・持続的生物資源利用に普遍的なものとに峻別して明確に示し、ワークショップ・セミナー等を通じ成果の共有とアジア地域の研究機関の研究レベルの底上げを図る。さらに、アジアの問題土壌地域の環境修復と生物資源の持続的利用という共通のゴールに向け、アジアと日本双方の若手研究者の人材の育成を念頭に置いた研究協力体制の強化と研究ネットワークの広域化を図る。
参加者
(日本側)
拠点代表者:福代康夫(東京大学アジア生物資源環境研究センター長)
コーディネータ:小島克己(東京大学アジア生物資源環境研究センター)
高野哲夫、津釜大侑、藤原一優、李学佳、鈴木雅也、大屋美知、小林紫緒、劉華、練春蘭、奈良一秀、木村恵、Yahua Chen、 黄建、蘇鈺、白子幸男、宮下脩平、太田達郎、鴨下顕彦、荒木祐二、Yen Nguyen、則定真利子、山ノ下卓、影山渓、山ノ下麻木乃、井上雅文、足立幸司、蒲池健、大前芳美、堀繁、木田悟、田代展子、玉那覇綾子、唐碧雲、加藤雅文、陸丹、王若雪、西坂涼(東京大学アジア生物資源環境研究センター)
宝月岱造、根本圭介、山岸順子、小林和彦(東京大学大学院農学生命科学研究科)
石田朋靖(宇都宮大学)
長野敏英、大澤和敏(宇都宮大学農学部)
吉野邦彦(筑波大学大学院システム情報工学研究科)
Makara Ouk、Sareth Chea、Sophors Heng 、Vang Seng(Cambodian Agricultural Research and Development Institute)
(中国側)
拠点代表者:Shenkui Liu(Northeast Forestry University)
Xinxin Zhang、Qingjie Guan、Shumei Jin、Qiuxiang Luo、Song Yu(Northeast Forestry University)
Xuanjun Fang(Hainan Institute of Tropical Agricultural Resources)
Huixin Li、Hongsheng Zhang、Zhenguo Shen、Jianmin Tao、 Jinchi Zhang(Nanjing Agricultural University)
Renfang Shen(Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences)
(タイ国側)
拠点代表者:Pisoot Vijarnsorn(Land Development Department, Acid Sulfate Soil Improvement Project under Royal Initiatives, Chaipattana Foundation)
Poonsak Mekwatanakarn、Boonrat Jongdee、Uraiwan Kotchasatit、Anuchart Kotchasatit、Varapong Chamarerk、Waraporn Wongboon(Rice Department)
Tanit Nuyim(Royal Forest Department)